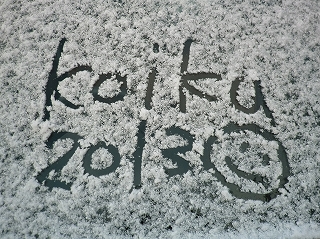
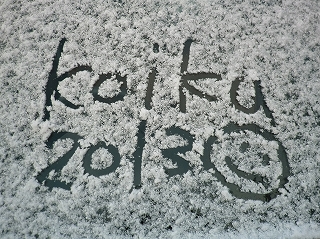
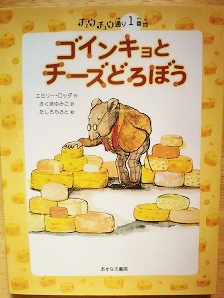
~ハツカネズミのすむネコイラン町にはチュウチュウ通りというすてきな通りがあります。その1番地にすむのは、お宝チーズをいっぱい持っているお金持ちネズミのゴインキョ。でも、ある夜のこと…。~
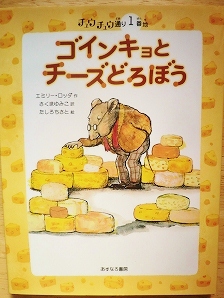
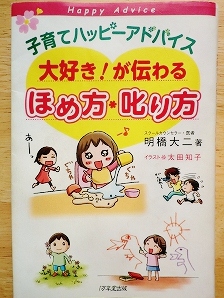
「子どもは一人ひとり違うのだから、子育てに絶対の正解などなく、子どもの数だけ正解がある。」よく聞く話ですね。もっともだと思います。“育児書”や“ネット情報”や“人の意見”に絶対の正解を求めるだけでは、振り回されるだけで終わるでしょう。しっかりと目の前の我が子を見つめ、自分を見つめて、心の声に正直に行動することが大切だと思います。
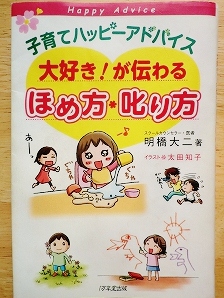

【 小さな失敗、小さな怪我を沢山させよう! 】
やってみる→うまくいく。あるいは失敗する→失敗を活かして違うやり方でやってみる。という試行錯誤のサイクルを自分でどんどん回していける子は賢くなります。公園では自分の体を使って試行錯誤が行われることが多いため、失敗すると文字通り、痛い目にあいます。わかりやすくていいですね。危険なことについて身を持って知るので、危機管理も上手になります。大きな怪我をしにくい環境ですので安心して野放しにできます(笑)。
「危ない!」と言って簡単に手を差し伸べているお母さんを公園ではよく目にしますが、「もったいないな~」と心から思います。「こんな危ないことして!」と叱ったりするのはもう理解不能です。“賢い子”
にするチャンスを自らつぶしている訳です。危機管理のできない“危ない子”を自ら作っている訳です。痛い目にあわせりゃいいんですよ。母親は父親と違って、そのように割り切るのは難しいのでしょうが、できるだけ手を差し伸べないことを意識した方が良いように思います。でも、親が腹をくくって手を離せば、意外と子どもは怪我しないんですよね~。うちの子も1才くらいからできるだけ手を離して、小さな怪我をする機会をいつも伺ってるのですが、敵も意外に慎重でなかなか怪我してくれません(笑)。
こけてすり傷くらいです。危ないことを察知する能力が磨かれていってるんですね。基本的に自分ができることしかしない。そうすると2才くらいからは本人任せ(というか野放し。笑)にできます。
危ないことを叱るお母さんの話を書きましたが、叱られている子を見てると、確かに危なっかしい雰囲気があるんですよね。目を離したら本当に危険なことをするかもしれない。だから手や口を出さざるを得ない。わかるんですけど、悪循環ですよね。こういうところから試行錯誤できない、指示待ちの考えない子になっていくのではないかと他人事ながら心配になります。取り返しのつかない大きな失敗や大きな怪我をする前に、どこかで勇気を出して見守る姿勢に切り替えるべきだと感じます。
冗談で“野放し”と書きましたが、実際には私も“見守る”ようにしています。完全に目を離すことはしません。とはいえケアするのは最小限。高い所から固い所に落ちること(0~2才)、車にひかれること(0~6才)、この二つくらいですね。後は経験を通して学ばせるのが一番だと思います。
たかが公園されど公園。 「信頼して任せても大丈夫なんだな、この子は勝手に自分で経験を積んで
勝手に伸びていくんだな」という実感を抱くことができれば、それは親子の幸せに繋がると思います。
というところで今回は終わりです。続きは後編で。


ではどうするか。一つはそういう場を作り出すこと。なかなか難しいですけどね。もう一つは、お父さん
お母さんが一緒に遊ぶ! 子ども同士で遊べる時間が短いのなら、やはり親子で一緒に遊ぶ時間は貴重です。それを楽しんでくれる年令が限られていることを考えると、たとえ忙しくてもその時間を確保する努力をすべきだと思います。
一緒に遊ぶときのポイントは言わずもがな、まずは自分が楽しむこと!ですね。子どもの遊びに付き合う、という意識を切り替えて、自分自身が率先して楽しむことが大切だと思います。一緒に楽しめることなら遊びの内容は何だっていいのでは。何はさておき没頭すること。携帯やスマホは見ない(笑)。自分の経験から、こちらの意識を集中して本気で遊ぶと、子どもの遊び心もビビッと刺激され、後は勝手に遊び始めることが多いように思います。子どもが遊びに没頭し始めたら、そのまま一緒に遊ぶもよし、自分のことをするのもよし、とにかく短い時間でも“完全に童心に返る”ことが大切な気がします。
最後に我が子の場合。平日午前中。娘も次男も勝手気ままに遊んでいることが多いので、そんな時は私はベンチでのんびり読書です。しかし遊びが停滞すると「いっしょにあそぼ~」が連発されます。意識を切り替える時です。遊びモード発動です。「よ~し。娘よ息子よ、今こそ父が人生の楽しみ方、
遊び方の見本を見せてやろう!真に遊べる人間は道具を必要としない。今ここにあるもので創意工夫して遊ぶのだ!」と気合を入れ周りを見回します。「枯れ葉・枝・土…以上。せ、せめて虫とか水とか花びらとかあれば…いやいや、真に遊べる人間は今ここにあるもので…う~~~ん、これはどうだ!」と頭をフル回転させて渾身の遊びを提案します。これ自体が“自分に挑戦”遊びなのです(笑)。時々は苦し紛れで考えた遊びがヒットして「おっ、けっこう楽しい!」と盛り上がります。これ気持ちいいです。しかし大抵は、悲しいかな「う…これ楽しいか?微妙…」という遊びしか提案できません(泣)。ところがそんな遊びでもきっかけさえ与えてあげれば、子ども達はそれを見事に発展させてグイグイと遊び始めるんですよね。結果、「ま、まけた…」と年をとり童心を失い頭を固くした自分を思い知らされることになるのでした…(笑)。